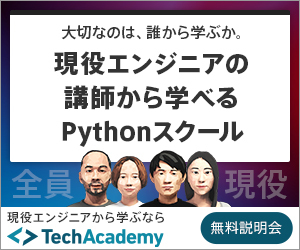学生から社会人、そしてシニア層まで幅広い世代の人々がプログラミング学習を始めています。
こういった一種のプログラミングブームが巻き起こっているわけですが、間違いなく言えることはどの家庭においてもほぼ普及率100%に近い状態でPCが存在していることが起因の一つになるでしょう。
特に学生や社会人であれば、PCを触れる機会が必ずといっていいほど訪れるかと思います。
そういった中で、いかに効率的に働くか、いかに自動化を図るのか、いかに稼ぐのか、などなど考えていった結果、プログラミング学習につながっていると感じます。
また、多くの観点からプログラミングの需要は高まってくることが予測されています。
現に、プログラミング業界に関する経済産業省などの調査データやIT人材白書と呼ばれる調査データにて、プログラミングの需要と将来性について、かなり詳しく解説されています。
エンジニア視点から見ても、時代背景からの推測から見ても、今後のプログラミングに関する成長速度は著しくなると考えられます。
今回の記事では、プログラミングの需要・将来性について、企業が求めるIT人材像や人材価値について徹底的に解説していきたいと思います。
エンジニアの需要について
ここではプログラミングに関する内容に入る前に、エンジニアとしての人材価値を考えることから始めます。
こちらは2015年度の経済産業省データになります。
こちらのデータを読み解くと、、、
・2015年時点で約17万人のエンジニア不足
・2020年に約37万人のエンジニア不足
・2030年に約79万人のエンジニア不足
これだけの人材不足の深刻化がデータとして現れているのが現状です。
人材不足が深刻化しているということは、世間からすればそれだけエンジニアを求めている状況にあると言えます。
さらにわかりやすいグラフがありましたので、こちらを参照すると、、、
・人材不足数は年々増加傾向にある
・供給人材数は年々減少傾向にある
人材不足に関しては、2030年での低位シナリオで約41万人、高位シナリオにおいては約79万人規模の人材不足が懸念されています。
また、供給人材数に関しても、人材不足が年々増加するわけなので、その分の人材供給率も低下してしまうため、年々エンジニア不足が加速することが予想されます。
そのため、IT業界ではエンジニア不足が騒がれている中で、エンジニア自体の需要は年々高まってきており、エンジニアとしての人材価値は貴重なものになっていきます。
エンジニアの将来性について
ここで考えなければならないのが、エンジニアの将来性についてです。
エンジニアといっても、SIer系企業やWeb系企業など、働く環境によっても求められるエンジニアは異なってきます。
つまり、求められるエンジニア像によってスキルが異なるため、スキルによっては将来性が変化します。
筆者自身、現在もエンジニアとして活動していますがSIer系企業で働いていた時は、社内の9割近くの人がプログラミング業務に携わっていませんでした。
たとえIT企業として動いていても、プログラミング業務に携わる人は限定的になっています。
もちろん、Web系企業であれば、自社製品・自社サービスを手がけることになるため、プログラミング業務をできることが基本として捉えられるかもしれません。
しかし、多くのIT企業であってもプログラミング業務を一般的にこなしているエンジニアはまだまだ足りていません。
そのため、プログラミング業務ができることはそれだけで人材として価値を高めることができます。
業界全体としてもエンジニア不足が深刻と予測されていますが、特にIT人材不足の深刻な分野としては、セキュリティ分野とAI・ビッグデータに関する分野となっています。
セキュリティ分野においては、2016年時点で約13万人のエンジニア不足となっており、2020年には約19万人のエンジニア不足が予想されています。
社外向けの情報セキュリティ対策業務を担当する人材について特に不足感が強いとされています。
また、AI・ビッグデータに関する分野では、2016年時点で1.5万人のエンジニア不足、2020年には約4.8万人のエンジニア不足と予想されています。
やはり先端IT技術に関するエンジニア不足では、「知識を十分に持った人材不足」「製品やサービスを具体化できる人材不足」といった課題が挙げられています。
IT業界の実情として、情報セキュリティ・AI・ビッグデータに関する分野は専門的な高いスキルを要求されるため、企業の中でもそれらを満たすエンジニアが求められていることになります。
裏を返せば、専門的な高いスキルを身に付けていくことは、これらの企業課題を満たすことにつながるため、エンジニアとしての市場価値を高めることになります。
そのため、これだけIT業界においても細分化された分野が確立した中で、エンジニアとしての生存戦略を考慮していかなければ、エンジニア自身も生き抜くことができない見通しが立ち始めています。
プログラミングの需要について
こちらは、IT人材白書2018年度の資料から引用しています。
日本におけるIT企業の調査データから、IT人材の”質”の不足感についての変化を読み解きます。
すると、、、
・「大幅に不足している」が25〜30%前後
・「やや不足している」が60〜65%前後
・不足に関する合計値は各年度で80%以上
調査データから、IT人材に対する”質”の不足感はかなり高いことが分かります。
では、これだけ多くの企業でエンジニアに関する”質”の不足感が高まっているのでしょうか。
さらに、深掘りしていきます。
エンジニアに求められる”質”とは
IT企業といっても、その中での働き方は会社によって異なり、所属しているエンジニアの業務内容も変化します。
しかし、それらを項目化して「価値創造型」と「課題解決型」と分類した時に、どのような人材がこれから求められていくのか、複合的に考えていきます。
エンジニアに求められる”質”に関して、左側のグラフは「価値創造型」を示し、右側のグラフは「課題解決型」を示しています。
価値創造型においては、「問題を発見する力(探索能力)・デザイン力」「新しい技術への好奇心や適応力」「独創性・創造性」が割合を高く占めて求められるものになっています。
また課題解決型においては、「IT業務全般的な知識・実務ノウハウ」「IT業務の着実さ・正確さ」の二つが割合が高く占めて求められることになります。
やはり、価値創造型と課題解決型では求められているスキルが異なり、価値創造型においては上記の内容の割合が非常に高いため、市場価値を高めるためにも強く求められているスキルであることが示唆できます。
ここで考えなければならないのが、IT業界が発展した際の技術進歩による業務変化です。
おそらくというよりは間違いなく、今後新たな技術が飛躍的に進歩し、エンジニアに対して求められるスキルは膨大になってくることが想定できます。
そこで、必要になってくるのがプログラミングというスキルだと考えます。
現在では、まだ多くのIT企業がプログラミング業務とそうでない業務を分けた形で動いていますが、今後のエンジニア不足と技術進歩による業務変化から、IT企業で働く人々はプログラミングを一般スキルとして求められると考えられます。
理由としては、、、
・新人に多くの時間とコストをかけられない
・業務経験を活かしたプログラミング業務が必要になる
・業界知識が備わっている人材を求む
やはり新人研修にも費用がかかったり、すでに業務経験や業界知識があれば、人材に対しての時間もコストも減らすことができます。
さらに、技術進歩によって業務が変化したとしても、業務内容は理解できている人たちなので、適応力が高ければ順応しやすいわけです。
そして、課題解決型であり価値創造型でもあるエンジニアに生まれ変わることが初心者より圧倒的に有利に進められるはずです。
今後も多くの最新技術から、新しいサービスが生み出されることが想像できますが、IT業界において自分自身で問題を発見し、取り組みながら解決していく力は人材価値が高いです。
ただ、サービスを創造(発想だけでとどまる)しただけで仮想環境内で具現化できないようでは、プログラミング業務ができるエンジニアの価値に追いつくことも追い抜くこともできません。
このように、多くのデータを読み解きながらIT業界の現状と照らし合わせていくと、エンジニア不足の深刻化から始まり、エンジニアに求められる”質”が存在し、課題解決型だけでなく技術進歩を考慮して価値創造型の人材にならなければ、生き残ることは困難になってきます。
そのため、プログラミングスキルを持っているということは、それだけ価値創造型の業務であっても取り組める可能性があるとともに、今後ますますIT業界の技術が進歩した時に、必須となるスキルになることでしょう。
プログラミングの将来性について
ここではさらに踏み込んだ話題として、今注目を浴びているAI分野を例にプログラミングの将来性について考えていきます。
こちらは、IT人材白書2019のIT企業のAIに携わる人材獲得・確保に対する調査内容になります。
調査したIT企業において、「AI人材はいる」が約14%、「AI人材はいないが、獲得・確保を検討している」が約28%、「AI人材はいない。獲得・確保の予定はない。未検討」が半数以上の約58%を占めています。
このことから、先端IT技術分野の一つであるAIですが、IT企業の中でもエンジニア獲得・確保以前に検討をしていない企業が多く存在していることが分かります。
しかし、今後のIT業界としてAI・ビッグデータといった先端IT技術が進歩していく上で、それらに強く関連する技術は間違いなく必須スキルとしてエンジニアが持ち合わせていかなければ、生き残ることは皆無です。
さらに、技術進歩によって多くの分野が成長することは、それだけセキュリティを高めた安全運用も視野に入れなければならないため、追随するように情報セキュリティ分野のエンジニアも市場価値を高めていくことになります。
IT業界の大手企業を始め、先端IT技術を駆使し始めれば、先端IT技術を利用しない企業と大きなビジネスにおけるギャップが生じるため、必ずどこかのタイミングで需要の爆発が発生するはずです。
これらの内容から、AIエンジニアの重要性は今後飛躍的に増加してくることが予想されます。
また、新しい技術を利用した新製品やサービスを開発する際に、ソフトウェア領域であるAI分野は確実にプログラミング業務が発生します。
ソフトウェア領域における各分野が成長するということは、同時にエンジニアにおいてプログラミングスキルが必要になってくることが示唆できます。
知識がどれだけあっても活用できなければ何も成果を出すことができません。
今後のITにおける市場価値をAI分野が担っていくことは予測できているので、それに伴い活用することができる人材は価値が爆発します。
これは、AI分野に限ったことではなく、IT業務全てにおいて今後求められる内容がプログラミングに傾き始めると考えられます。
なぜなら、実現可能かどうかを判断・創造できるのは、ソフトウェア領域であればプログラミング業務に他ならないからです。
これからのソフトウェア領域の技術を担う若年層のエンジニアにとって、課題解決型だけに留まらず価値創造型の業務も行えることで、エンジニアとしての価値を高めるとともに、必須スキルとしてプログラミングが必要になってくるでしょう。
まとめ
エンジニアにおけるこれからの需要と将来性、プログラミングにおける今後の需要と将来性、ソフトウェア領域に関しての考察等をまとめてきました。
エンジニアにとって、今後製品・サービスを生み出す仕事は減るどころか増えていくことが予想されます。
そのため、エンジニアの需要と将来性は、市場に対して人材価値が高まる一方なので、安定しているように感じます。
しかし、働いていく中で求められるスキルはどんどん変化し、プログラミング業務の重要性が問われてくることが予測されます。
これから、IT業界でプログラミングスキルを駆使して働きたい人や、すでに業界で働いている人であっても、成長することを前提に業務へ取り組まなければ人材価値を失いかねません。
それほどまでに、IT業界の成長速度は著しいため、常にプログラミングスキルを磨き続けていくことがエンジニアにおける需要と将来性を確保できる方法になるでしょう。
最後まで一読していただき、ありがとうございました!